今回は【自己有用感】について
お話ししたいと思います。
【現役保育士が子どもにお礼する時、5割増しで感謝を伝える理由】

突然ですが、自己有用感ってご存知ですか?
自己有用感❓
初めて聞く方もいらっしゃると思います。
1. 自己有用感とは?
自己有用感(じこゆうようかん)とは、
「自分は誰かの役に立っている」
「自分の存在や行動には意味や価値がある」
と感じる気持ちのことです。
簡単に言えば、
「自分はここにいて良いんだ」
「私にはできることがある」という感覚です。
幼児期に自己有用感が育つと、
✨ 自信と自己肯定感が高まる
✨ 挑戦する意欲が生まれる
✨ 人との関わりに前向きになる
✨ 良好な人間関係を築く力が育つ
✨ 失敗にもくじけない
✨ ストレスへの耐性が強くなること
などが挙げられます
2.自己有用感の特徴
1. 役に立っている実感
家族や友だち、社会の中で
「自分の行動が誰かの助けになった」
「貢献できた」と感じること。
2. 存在価値の実感
何か特別なことをしなくても、
「ここにいるだけで大切な存在だ」と思えること。
3. 成長の原動力
自分が役に立つ経験を積むことで自信が生まれ、
新しいことに挑戦する意欲がわいてくる。
3.幼児期における自己有用感の例
子どもが「役に立った」「自分もできる」と感じられるのは、
日常生活の中にたくさんのチャンスがあります。
👍 お手伝いの成功体験
例えば、保護者が
「テーブルにスプーンを並べてくれる?」と頼むと、
子どもは「自分も家族の役に立てた!」と感じます。
その際、「ありがとう」「とても助かったよ」と
言葉を添えると、さらに効果的ですね✨
👍 小さな達成感
洗濯物をたたむ、靴を揃える、
植物に水をあげるなど、小さな行動でも
「やりきった!」と感じられると
自己有用感が高まります。
👍 成功を共有する経験
公園で「見て!こんなに高く登れたよ!」と
親に報告する場面も、
承認されることで自信に繋がります✨
4.自己肯定感との違い
⭐️ 自己有用感:「自分は誰かの役に立てる」という感覚。
⭐️ 自己肯定感:「ありのままの自分で大丈夫」と感じる気持ち。
この2つは深くつながっていて、
自己有用感が育つことで自己肯定感も強くなります。
5. 保護者ができること
幼児期に自己有用感を育むために、
保護者が日常生活でできる工夫を紹介します。
✅ 「ありがとう」と感謝を伝える
何かを手伝ってくれたとき、
「助かったよ」と言うだけでも
子どもは「自分が必要とされている」と感じます✨
✅ 「あなたに任せるね」と期待を伝える
たとえば、
「今日はお花に水やりを手伝って」と言うと、
子どもは「自分の役割がある」と認識して、
とても頑張ってくれます。
✅ 失敗を責めず、挑戦を褒める
お手伝いで、牛乳をこぼしてしまったとしても、
決して責めないでください。
「こぼしたのは残念だったね。
でもお手伝いしてくれて嬉しかったよ」と
ポジティブな言葉をかけてみてください👍
6. 自己有用感を阻害しないための注意点
一方で、以下のような行動は
自己有用感を損なう可能性があります。😫
🔽 過度に手助けしすぎる
子どもが自分でやろうとしたときに
「まだ早いから」と止めてしまうと、
自分を無力だと感じることがあります😫
🔽 否定的な言葉をかける
「なんでそんなこともできないの?」
という否定的な言葉は、自信を失わせる原因に。
代わりに「次はこうしてみようね」と
前向きな声かけを心がけましょう。☺️
🔽 結果だけを評価する
絵を描いたとき、「上手だね」だけではなく、
「たくさんの色を使って工夫したんだね」と
プロセスを褒めると効果的です。
まとめ
幼児の自己有用感を育てることは、
子どもの心を豊かにし、
自立心やチャレンジ精神を育む
大切な土台となります。
幼児期に自己有用感が育つと、
⭐️ 挑戦する力(主体性)
⭐️ 他者とつながる力(協調性・共感力)
⭐️ 自分を大切に思う力(自己肯定感)
がしっかりと根づきます。
これらは、子どもが将来、
さまざまな困難に立ち向かう際の強い支えとなります。
家庭や保育の場で、小さな成功体験や
人とのつながりを積み重ねることが大切です😊
日常の中で、小さな「できた!」や
「ありがとう」の積み重ねが、
将来的な自信や自立心を育むのです。
皆さんのお子さんが、
「自分は誰かの役に立てるんだ」と
感じながら成長していけるよう、
ぜひ参考にしていただけたら嬉しいです😊✨
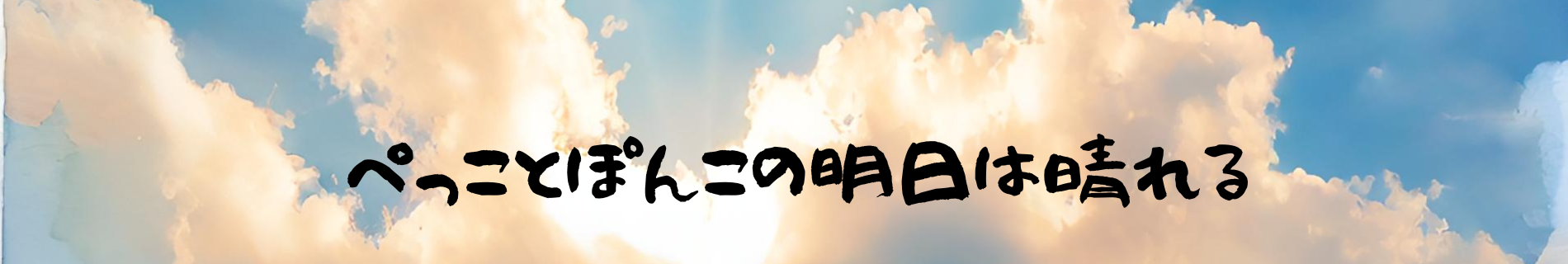
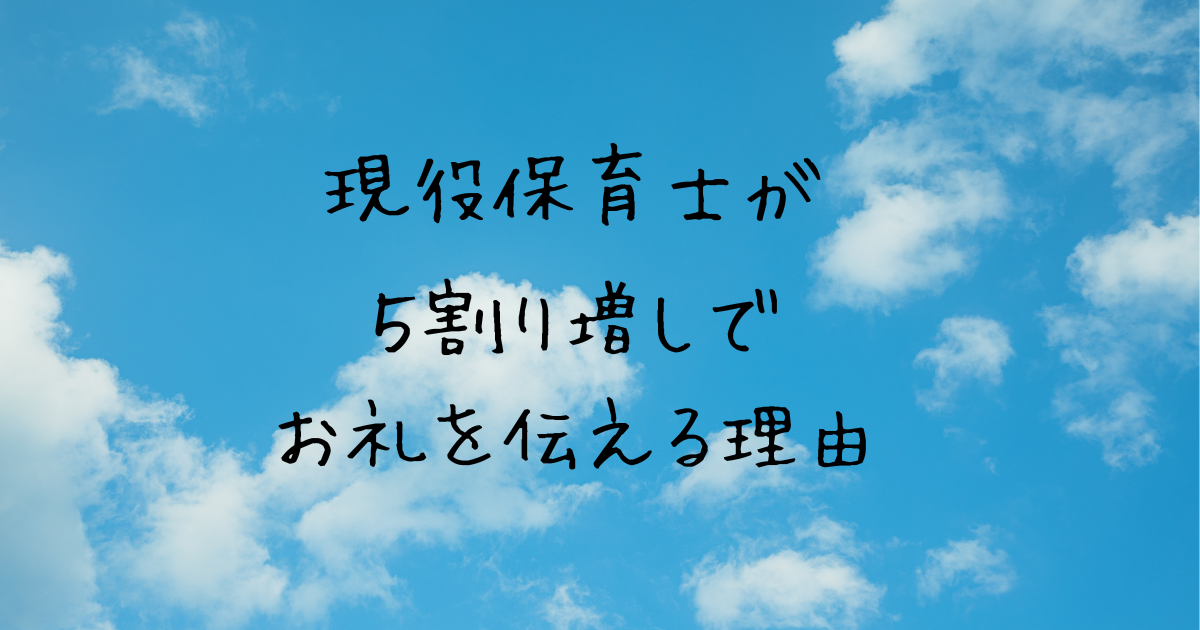

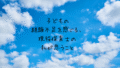
コメント